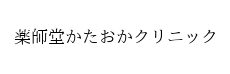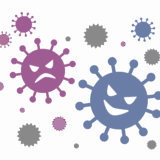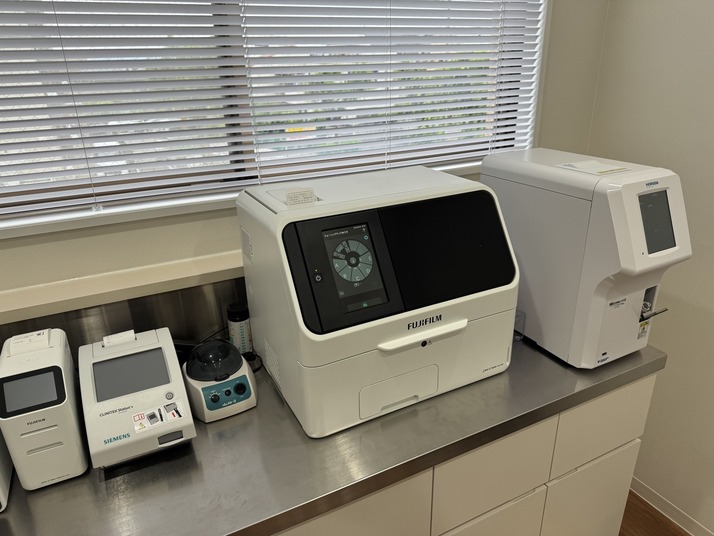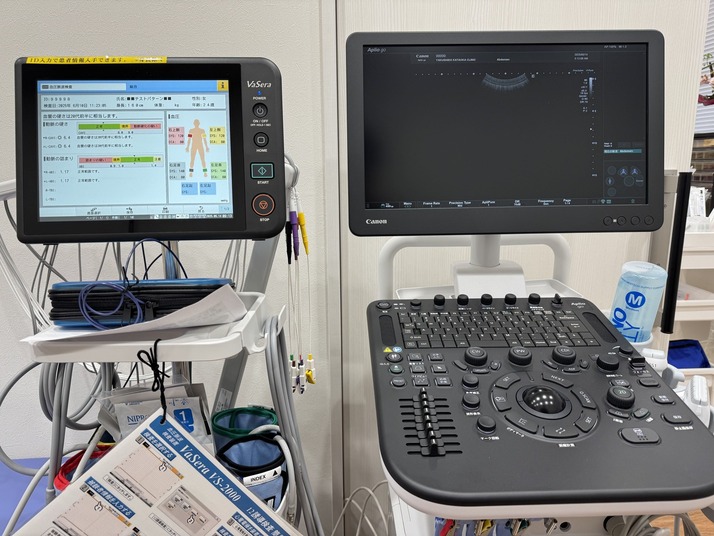肥満症
単に体重が多いというだけでなく、健康に悪い影響を及ぼす肥満を「肥満症」といいます。
肥満そのものが病気を引き起こす場合、または肥満によって他の病気が悪化する場合に診断されます。
日本肥満学会の定義では、BMI(体格指数)25以上を「肥満」とし、そのうち健康障害(高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症・睡眠時無呼吸症候群など)を伴う場合を「肥満症」と呼びます。
肥満の判定基準(BMI)
| 区分 | BMI(体重[kg] ÷ 身長[m]²) | 判定 |
|---|---|---|
| 18.5 未満 | 低体重(やせ) | 栄養不足に注意 |
| 18.5〜24.9 | 普通体重 | 標準的な体型 |
| 25.0〜29.9 | 肥満(1度) | 生活習慣の見直しを推奨 |
| 30.0〜34.9 | 肥満(2度) | 医師による管理が必要 |
| 35.0〜39.9 | 肥満(3度) | 専門的治療が必要 |
| 40以上 | 肥満(4度) | 重度肥満、合併症リスク大 |
肥満症が問題となる理由
肥満は単なる「体重の問題」ではなく、生活習慣病の根本的な原因となることが多いです。
以下のような疾患のリスクが高まります:
・高血圧症
・糖尿病(2型糖尿病)
・脂質異常症
・高尿酸血症(痛風)
・心臓病・脳卒中
・睡眠時無呼吸症候群
・脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患:NAFLD)
肥満の原因
・エネルギー摂取量(食事)が消費量より多い
・運動不足、デスクワーク中心の生活
・睡眠不足やストレスによる食欲亢進
・加齢やホルモンバランスの変化
・遺伝的・体質的要因
治療
1. 食事療法
・「腹八分目」を意識し、摂取カロリーのコントロール
・炭水化物・脂質・タンパク質のバランスを整える
・野菜・海藻・きのこ類などで食物繊維を摂取
・間食や甘い飲料を控える
2. 運動療法
・1日30分程度の有酸素運動(ウォーキング・サイクリングなど)を週3回以上
・無理のない範囲で継続することが大切
・筋肉量を維持・増やすと基礎代謝も上がります
3. 行動療法
・体重や食事内容を記録する習慣
・睡眠・ストレス管理の改善
4. 薬物療法(必要な場合)
・生活習慣改善で効果が得られない場合に検討
・医師の指導のもと、肥満症治療薬(GLP-1受容体作動薬など)を使用することもあります
当院での取り組み
当院では、肥満の原因を丁寧に分析し、無理のない減量目標を一緒に立てていきます。
食事・運動・生活リズムの改善を中心に、医学的根拠に基づいた体重管理をサポートします。
必要に応じて、管理栄養士による食事指導や薬物療法も行います。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 「肥満」と「肥満症」はどう違うのですか?
A. 「肥満」は体重が多い状態を指しますが、「肥満症」は肥満によって健康障害が生じている状態をいいます。単なる体重の問題ではなく、治療が必要な「病気」です。
Q2. ダイエットを始めても続きません。どうすればいいですか?
A. 無理な食事制限や短期間の減量はリバウンドの原因になります。小さな目標を立て、週1回の体重チェックなど「続けられる方法」を一緒に探すことが大切です。
Q3. 少し太っているだけでも病院に行った方がいいですか?
A. 健康診断で血圧・血糖・コレステロールなどに異常がある場合は、肥満が関係している可能性があります。早めの相談で生活習慣を見直すことが、将来の病気予防につながります。
Q4. 薬でやせることはできますか?
A. 近年はGLP-1受容体作動薬など、肥満症に保険適用される薬も登場しています。ただし、生活習慣の改善が治療の基本です。薬はあくまで補助的に使用します。(近日中に肥満治療薬について解説するページを作成します)